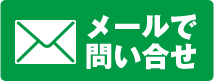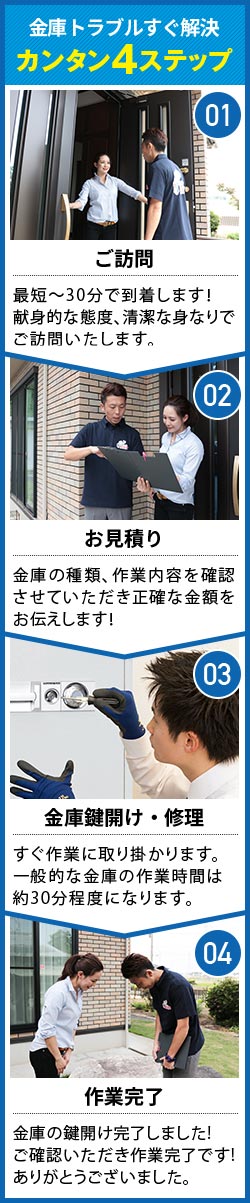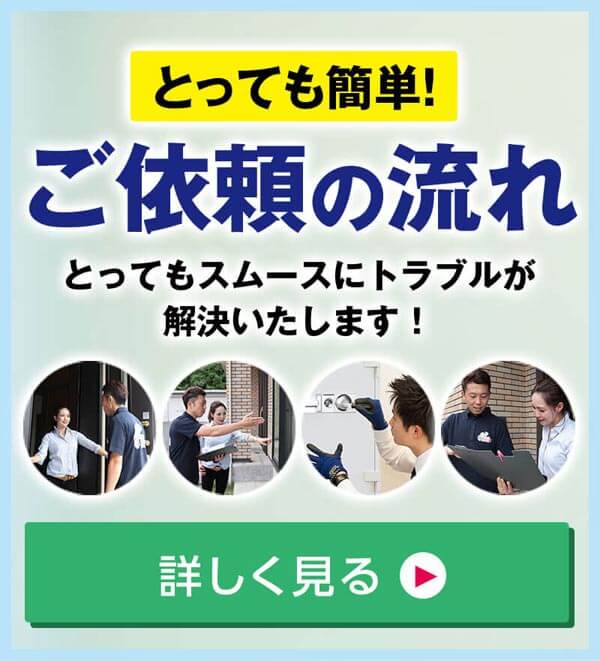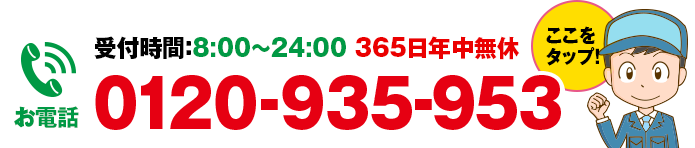金庫の種類とタイプ別の特徴を詳しく解説

耐火金庫とは?
耐火金庫とは、厳格な基準をクリアした金庫となります。耐火金庫の場合、火災時でも金庫の中のものが焼失することはありません。それだけの性能が備わっている金庫が耐火金庫なのです。
耐火金庫の性能はJIS(日本産業規格)により、5ランクに区分されています。
その内訳は、0.5時間、1時間、2時間、3時間、4時間耐火型となり、この数字は、金庫の耐火時間を表すものとなります。
この試験をクリアする基準には、収納物が一般紙用の場合で、
- 試験のあいだ、金庫内の温度が177℃以下に保たれる。
- 試験中に金庫内に入れておいた新聞紙の文字が読める
ことが合格基準となります。
また、フレキシブルコンピュータディスク用の場合では、
- 試験のあいだ、金庫内が下記の状態に保たれる。
- 温度52℃以下/湿度80%以下
が合格基準となります。
ただし、必ずJIS(日本産業規格)の試験に合格しなければいけないという決まりはなく、金庫のメーカーによっては、UL耐火性能試験 (アメリカの企業Underwriters Laboratoriesによる試験)やETL耐火性能試験 (イギリスの企業Intertek Group plcによる試験)などといった海外の耐火性能試験をクリアしている耐火金庫もあります。
このような基準をクリアしている耐火金庫。耐火金庫の大半は、中が空洞となるスチール(鋼鉄)のボディーに気泡コンクリートを充填した構造となります。この気泡コンクリートが耐火材となる仕組みです。
発泡剤を使用しコンクリートの内部に多数の気泡を閉じ込め多孔質化させ作るものとなります。また、この気泡コンクリートには、結晶水と自由水という2種類の水分が含まれています。
そして、この気泡コンクリートは耐熱性も備え持っており、火災が起きた際、水分が気化し、その気化熱により金庫内を冷却することが可能です。また、気化した蒸気は扉の隙間から噴出するため、金庫内への炎や煙の侵入を防ぐこともできるといった仕組みとなります。
防盗金庫とは?
金庫の中でも最強と言える防盗金庫。
防盗金庫は泥棒に強く、そして、耐火性も持ち合わせているため、最強の金庫と言えるのです。
そして、この防盗金庫と名乗ることができるのは、以下のような厳しい検査に合格した金庫のみとなります。
防盗金庫の定義は、日セフ連(日本セキュリティファニチュア協同組合連合会)により実施される防盗基準をクリアしたものとなります。もちろん、防盗金庫の場合、耐火性も必要となるため、耐火試験にも合格していることが前提です。
試験の種類は2つ!「耐溶断・耐工具金庫」と「耐工具金庫」です。
耐溶断・耐工具試験
耐溶断・耐工具試験は、大掛かりな破壊行為を想定した試験となり、ガス溶断機、電動工具などを用いて試験が行われます。
耐工具試験
耐工具試験は、電動工具など簡易的な工具を使用した破壊行為を想定した試験です。
試験を受ける際には事前に図面を提出することになり、その提出された図面をもとに弱点などを検討したうえで決められた工具を使用し3種類の破壊試験を行います。
- 1つ目はA 系列:施錠機構への攻撃
- 2つ目はB 系列:扉及びカンヌキへの攻撃(扉こじ開け)
- 3つ目はC 系列:侵入口を空ける(φ 100mm)
です。
防盗金庫において、重要なのは対破壊性能と言われています。実際、金庫の中のものを持ち去ろうとする泥棒は、ピッキングなどで鍵を開けるのではなく、扉を無理矢理こじ開ける、破壊するといった行為が圧倒的に多いのです。そのため、防盗金庫において大切なのは、いかに破壊されない金庫であるとかということになるのです。
これにより、防盗金庫は電動ドリルやハンマーなどで破壊されない構造に作られています。そして、この構造は各メーカーによって企業秘密となります。多くの防盗金庫では、パネルに衝撃や熱から守ることができる特殊合金を用いていると言われ、こじ開け対策としては、多方向のロックが可能なカンヌキ構造が用いられていると言われています。
投入式金庫とは?
投入式金庫は、上段が投入口、下段が取り出し口に分かれる2段構造の金庫となります。
上段の投入口から、その日の売上金などを入れると下段にそのまま落下。そして、落下した売上金などは、下段からしか取り出すことができず、その下段の鍵を管理する人のみが鍵を開け取り出すことができる仕組みになっています。
この投入式金庫の場合、一度、上段の投入口から下段に落下したものは上段から取り出すことが非常に難しいという点です。そのため、管理者が不在の場合でも安心し売上金などを保管することができる仕組みとなっています。
このような特性を生かし、投入式金庫は店舗オーナーの大きな力となっています。
例えば、24時間営業の店舗の場合、日々の売り上げは毎日、金融機関の夜間金庫を利用しているという場合も多いと思われます。その場合、毎回、金融機関まで足を運ぶといった労力が必要となります。また、売上金を
夜間に外に持ち出すといった危険性も考えられます。
そのほか、店舗オーナーの悩みとして、
- 日々の売り上げが合わない
- 従業員の誰かが売上金の抜き取りを行っている
- レジ締めを不特定の従業員のお願いしている
といったことにより、疑いたくない人を疑わなくてはならない場合も少なくありません。
こういった店舗オーナーの悩みを解消することができるのが投入式金庫なのです。
投入式金庫の場合、数日分の売り上げを保管することができる容量の金庫も多く、数日間、安心し利用することも可能です。サイズだけではなく、何を投下することができるのか?などといったバリエーションも豊富なため、売上金意外に保管したいものがある場合は、何を投下することができるのか、といった大きさなどを確認し投入式金庫選びを行うことをおすすめします。
手提げ金庫とは?
手提げ金庫は、その名前からもわかるように手に持って移動させることができる小型の金庫となります。取っ手が取り付けられているものがほとんどで、そう重いものではありません。
手提げ金庫の中に保管することができるものは、お札や小銭だけではなく、通帳やクレジットカードなどのカード類といったものなど、なんでも保管することができます。また、手提げ金庫には付属品として、小銭、お札トレーやコイントレースタンド、コインカウンター表示があります。
手提げ金庫の使用用途としては、
- 売上金を銀行に預ける一時的な保管場所
- 会社の小口現金管理
- 出張店舗の際の売上管理やレジ代わり
- 貯金箱代わり
などと利用する人に合わせ、様々な用途で利用することができる金庫となります。
サイズは、主にA4サイズ、A5サイズ、B5サイズなどとなり、同じメーカーの手提げ金庫でも、サイズによって金庫の中の構造や機能などが異なる場合があります。そのため、大きさだけではなく、どのような構造になっているのか、どのような付属品が備わっているのか、などを確認し購入を検討する必要があります。
鍵の種類も様々で、
- 鍵を差し回すだけのシリンダー錠のみのタイプ
- ダイヤル番号のみのダイヤル錠タイプ
- シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックタイプ
- シリンダー錠とテンキー式のダブルロックタイプ
などがあります。
そのため、手提げ金庫選びを行う際は、大きさ、付属品、鍵の種類と3つの確認を行い選ぶことが大切です。